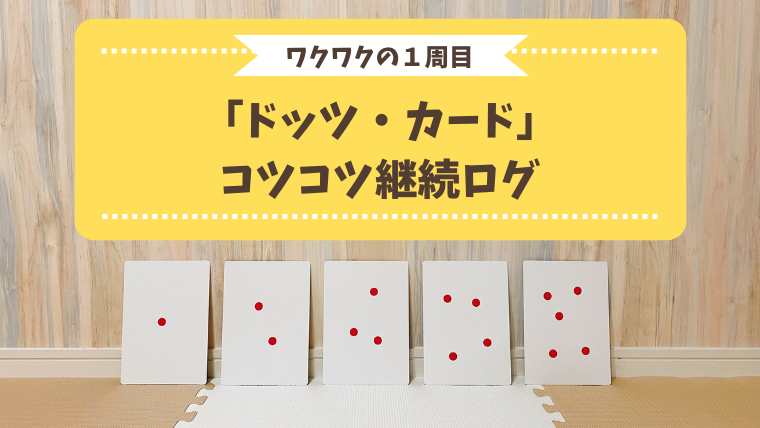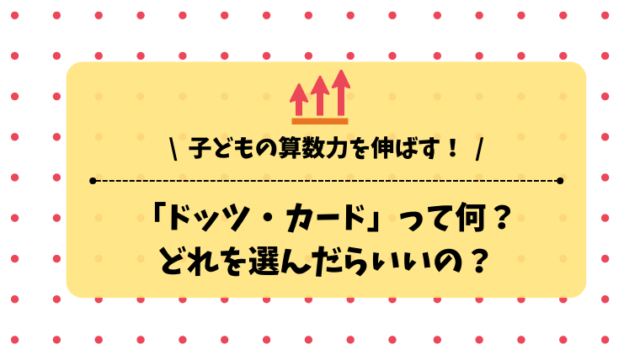この記事では、実際の「ドッツ・カード」の取り組みや子どもの様子について書いています。
「ドッツ・カード」って実際どうなの?と思われる方、多いと思います。
私自身もそうでした。
「ドッツ・カードをやっていたから子どもの算数力が伸びた」等の成果は評価できないのですが、そもそも実際に続けられるのか?我が家の場合の取り組みの様子を記録していきたいと思います。
この記事は以下のような人にオススメです!
- これからドッツ・カードを購入しようか悩んでいる
- 実際に続けられるのか心配
- 他の方がどうやって取り組んでいるのか知りたい
はじめに。使用したドッツ・カードについて
ドッツ・カードの種類は「家庭保育園」「七田式」「KUMON」があり、手作りすることも可能です。
(「家庭保育園」は現在販売終了となっているため、中古のみとなっています)
その中でも、私は七田式「ドッツ・セット」を使用しています。
ドッツ・カードの種類については、別記事にて紹介していますので、参考になさってください。

私が七田式「ドッツ・セット」を選んだ理由は下記の3つです。
- 枚数が多く手作りは大変
- そに日に実施する分がすでにセットされており、手間がかからない
- カードによってイラストが異なるので、子どもがよく見てくれそう
「ドッツ・カード」の取り組み記録
七田式「ドッツ・セット」に取り組んだ様子を1か月ごとに書いていきます。
かっこ()内は、その時の子どもの月齢を表しています。
例:0y7m→0歳7か月児、1y2m→1歳2か月児
1日目(0y6m)
重たい段ボールをワクワクした気持ちで開け、早速「ドッツ・カード」を始めました。
| 取り組みの満足度 | ★★★★★ |
| 子どもの様子 | 新しいおもちゃを見つけた時のように、キラキラした瞳でじっとカードを見てくれる。 視線がぶれることもなし。 |
| 取り組みの工夫 | 1日1回実施。 「リズムよく」「読み間違えてもそのまま読み続ける」ことを意識。 ページをめくる際に、手がイラストにかぶらないように注意が必要。 |
1か月後(0y7m)
| 取り組みの満足度 | ★★★★✰ |
| 子どもの様子 | 時々視線がぶれるが、カードを見ていることが多い。 近くで読み上げると、カードを取ろうとする。 |
| 取り組みの工夫 | 環境は特に工夫していないが、興味がそれることが多くなったため、1日1回以上(なるべく複数回)実施。 |
2か月後(0y8m)
数式が難解になり、読み上げることに時間がかかるようになった。
| 取り組みの満足度 | ★★✰✰✰ |
| 子どもの様子 | 初めはチラッとカードを見るが、すぐ他の物に興味を示し、カードを見てくれない。 カードを収納している白い封筒に興味を示す。 |
| 取り組みの工夫 | 視覚的な刺激の少ない部屋の隅で実施。 1日1回以上行う。 |
1周目終了(0y8m)
帰省などで数回「ドッツ・カード」を実施できないこともあり、74日目で1周目を終了しました。
最終日の様子は次の通りです。
| 取り組みの満足度 | ★✰✰✰✰ |
| 子どもの様子 | ほとんどカードを見てくれない。 部屋の隅で、周囲におもちゃがない状態で行っても、すぐに方向転換し別の場所へ行ってしまう。 |
| 取り組みの工夫 | 1日1回以上行う。 視覚的な刺激の少ない部屋の隅で実施。 子どもが見ていない間も、カードはリズムよく読み上げ続ける。 |
まとめ。やってみて感じたこと
子どもが成長するにつれて動きが増え、興味の幅も広がるため、「ドッツ・カード」を行う難易度が上がっていくことをとても実感しています。
そのため、もし「ドッツ・カード」をしたいと思われているのならば、なるべく早く始めたほうが良いと思います。
「田式「ドッツ・セット」は毎回イラストが異なるので、まだ飽きにくい方なのではと思います。
「ドッツ・カード」は継続することがとても大切です。
具体的な期限を決めてはいないのですが、これからも記録を続けていきたいと思います。
効果が実感できる状態ではありませんが、「子どもに負担が少ない」「少しでも将来のためになるのなら」という思いで続けています。